おはようございます!ミヤビです(^^)
今日は『独身・無職・実家暮らしの課題を考える』というテーマで書いていきます。
ちょっと重めのテーマかもしれません。
決して他人事ではなく、ボクには41歳の実の弟がいて、まさにその状態であるということから感じていることを、少し踏み込んで書いてみます。
あくまで「否定」や「攻撃」を目的とする記事ではありません。
就職氷河期世代の課題や悩みにも関連することだと思いますし、日本社会において、同じような悩みや葛藤を抱える家族が多くいるのではないかと思うので、言語化していきます。
「無職・実家暮らし」という生き方は悪なのか?
まず最初に伝えておきたいのは、「実家暮らし」「独身」「無職」そのものが悪いわけではありません。
世の中には、さまざまな事情があります。病気、メンタルの問題、社会とのミスマッチ、失業、家庭環境…。
その背景にあるものを一括りにして否定することは、すごく乱暴なことです。
しかし、だからといって「すべてを許容し続けてよいのか?」という疑問も、同時に生まれてきます。
ボクの弟の場合、以前はアフィリエイトやブログといったネットビジネスに取り組んでいたようですし、今も何か継続はしているようですが、大きな成果はほとんどなく、表立った収入も確認できません。
うまくいっているのかどうかは明確に言わないので、実態は正直に言ってわかりませんが、まぁたぶんうまくいっていないんだと感じています。
ある意味先見の明がある人だな、と思っていて、弟である前に人として尊敬する部分はあります。
ただ、もう10年以上今の状態なので、何と言うか方向性や取り組みが間違っているような気はしています。
ボクの実家はお寺ですが、今も実家に住み、両親に世話になりながら住んでいるのが現実です。

家族の視点から見た「自立できない大人」のリアル
40代も後半に差しかかると、親の高齢化は確実に進みます。
ボク達兄弟の両親も70代。
現在は大きな病気はないですが、健康状態も少しずつ不安が出てくると思います。
同年代の親戚の叔母さんが最近突然死したこともあるので、いつそういう事態が起こってもおかしくないなぁ、と感じています。
そんな中で、弟がまったく経済的に自立していないという事実は、正直に言って不安材料でしかありません。
仮に親が亡くなった後、弟はどうやって生活していくのか?
その時、「長男であるボク」はどういう行動をしたらいいんだろうか?
頼られる未来はあるのかな、とも考えて胸の奥にモヤモヤが残ります。
家族だから、助けたい気持ちがゼロではありません。
でも、無限に助け続けることはできません。
そして、「支援する側」もまた、心をすり減らしていくのです。
自立しない理由は何か?
弟は決して「怠け者」ではないと思います。
若い頃から人よりも早くパソコンを扱い、ブログやアフィリエイトにも意欲的に取り組んでいました。
何を目指すつもりか分からなかったですが、宅建書士の資格も取得したそうです。
ボクが言うと身内への依怙贔屓(えこひいき)のような感じになりますが、勉強ができる頭の良い人なんだと思います。
しかし、継続的な成果が出せず、就職もしないまま今に至っている状態です。
時代の波に乗れなかったのか、向いていなかったのか、メンタルの問題があるのか…。
正直、本人に詳しく聞いたことはないですが、自らを「要件人間」「他人に興味がない」と言い放ち、壁を作っているようにも見えます。
「居心地の良い実家という環境が、自立を遠ざけてしまった可能性」は否定できないと思っています。
「家庭内ニート」問題と社会的孤立
近年では、「8050問題(80代の親が50代の子を支える問題)」という問題があるようです。
長期にわたる実家暮らし・無職・社会的孤立は大きな社会課題となっています。
以下、ChatGPTの回答です。
「8050問題(はち・まる・ごー・まる問題)」とは、80代の親が、50代の無職・非正規雇用・引きこもり状態の子どもを支え続けている家庭の問題を指します。1990年代以降に顕在化し、2010年代から本格的に社会問題として注目されるようになりました。
◆ 背景と由来
この言葉は、「80代の親(80)」と「50代の子ども(50)」という年齢層にちなんで名付けられました。
1990年代のバブル崩壊、就職氷河期、リストラ、非正規雇用の増加などが重なった世代(主に1970年代前後生まれ)が、社会的に自立しづらく、結果として「中高年の引きこもり」となるケースが増えています。
◆ どんな問題が起きるのか?
- 親の高齢化・介護問題
- 親自身が要介護状態になったとき、経済的にも身体的にも家庭が破綻しやすい。
- 子どもの孤立
- 長年引きこもりや就労経験の少ない状態で社会復帰が難しくなる。
- 親亡き後の生活困窮
- 親が亡くなることで収入源(年金など)が絶たれ、住む場所や生活手段を失う。
- 社会的孤立
- 家族ぐるみで外部と関わらず、地域からも孤立しているケースが多い。
◆ なぜ深刻なのか?
「8050問題」は、単なる家庭内の話にとどまらず、以下のような社会的コストや影響を及ぼします:
- 生活保護や医療費などの公的支援の増加
- 介護・福祉人材の負担増
- 高齢者と中年層のダブル孤立
- 家庭内の高齢者虐待や心中の危険性
◆ 解決の糸口は?
- 地域の福祉や就労支援との連携
- 家族ではなく第三者が介入する仕組み(NPO、自治体、支援団体など)
- 子の就労支援だけでなく、親の意識改革も必要
◆ まとめ
8050問題は、「時間の経過とともに悪化する可能性が高い問題」です。
早期の気づきと、小さな変化の積み重ねが重要です。
弟の場合、まだ40代前半ですが、兆しは似ていると思います。
- 日中に誰とも話さない日がある
- 他人との交流を避けがち
- 働くことへのモチベーションがあるようだが行動しない
- 生活のリズムが乱れていて体調を壊しがち
こうした日々を何年も繰り返すうちに、社会との接点がなくなり、「働く・稼ぐ・人と関わる」ことがどんどんハードルになっていくのです。
本人も苦しいと思いますが、家族も苦しい。
そして、誰も何も動けないまま、年月だけが過ぎていきます。
いつかゲームオーバーになるゲームをやっているだけ
ボクが今、「親がまだ元気なうちに、弟の今後を一緒に考える」というのは「余計なお世話」なのかもしれません。
ちょっと冷たいようですが、本心を言えば「知らんがな。好きに生きてよ」という気持ちもあります。
すごく自分勝手かもしれませんが、自分に影響があるかもしれないから考えているだけかもしれません。
現実的に考えて、親も弟も「いつかゲームオーバーになるゲームをやっているだけ」に見えます。
今は売り手市場で仕事があると言われていますが、40代の就職や転職活動が相当厳しいのは過去に書いている通りです。
日本の将来も楽観できるわけではないので、景気が悪くなったらまた無職になる人も増えていくし、歴史はきっと繰り返します。
今、自らゲームチェンジをしないと危ないんじゃないかな?とボクは思っています。
「大人としての責任」と「家族だからこその限界」
ボク自身はブログで書いたことあるかわからないですが、弟に対して怒りや苛立ちを含む「複雑な感情」を持っています。
- 「なぜ働かないんだろう?」
- 「どうして40歳を過ぎても自立しないのよ?」
- 「俺だってしんどいけど、なんとかやってるのに…」
- 自分はずっと実家にいてずるいな
こういう気持ちは正直言って今でもあります。
でも、感情をぶつけたところで、何かが劇的に変わるわけではないのです。
「他人と過去は変えられない、自分と未来は変えられる」とボクは考えているので、他者を変えようと心から思ってはいないです。
ボクたちはみな、大人です。
弟もまた、40歳を過ぎた「大人」です。
いつまでも「親に養われることを前提とした生活」では、どこかで限界が来ます。
本人も薄々分かっていることなのですが、直視していないんだと思います。
家族の一員として、何ができるか?
そして、「できること」と「できないこと」をどう線引きするか?
これが、ボクにとっての課題のように感じています。
弟を甘やかす母親、関係が悪い父親
母親というのは子どもには甘いようです。
両親も70代なので、弟がいることで助かっている部分があると思います。
この点に関してはボクも親の近くにいてくれてありがとう、という気持ちはあります。
別にボクもいたくなくて近くにいないわけじゃないんですけどね。
弟のことを「親に甘えてるよなぁ」みたいなことをたまに母親に言うと、「でもいてくれて助かっている」みたいなことを言われます。
まぁそれはそうなんだろうけどね、、、と思ってしまいます。
父親とはほとんど会話もなく、小さな父親の行動に対していつも苛立ちを募らせています。
気持ちはわかりますが、世話になっている以上その構造も歪に見えます。
そんなに嫌なら出ていって生活すればいいのに、と思いますが極論でしょうか?
家族ができること
結局、家族は一番身近な他人でしかありません。
ボクがこのことを考えるのは、前述したように『余計なお世話』かもしれないですし、ボクが考えることでもないです。
ただ、兄弟や家族ということで無償の愛みたいな感覚もあるのかもしれません。
何と言うか兄貴は弟のことが心配なんですよね。
人によってできることは違いますが、ボクは彼の人生を応援し続けることしかできないかな、と思います。
馬を水飲み場に連れて行くことはできますが、水を飲ませることはできないですし、飲むと選ぶのは本人次第なんですよね。

余談:パチンコをする家族
これは余談です。
マイナスプロモーションにしかなりませんが、ボクの家族はパチンコが趣味の一つです。
これを書くと家族が誤解されてしまいそうですが、事実なので書いておきます。
ボクも過去にパチンコにのめり込んでいた時期があります。
今はほとんどいかないですが、家族と行くことは1年に1~2回くらいあります。
ハッキリ言って親に教えられたので、親の影響ですよ(笑)
ものすごく矛盾しますが、本質的にはボクはギャンブルは嫌いです。
子どもの頃、実家で親戚の叔父さんや両親が集まって麻雀をやっていましたが、その光景が本当に嫌でした。
亡くなった祖父も競艇だか競輪で借金を作った人だったと聞いたこともあります。
そんなに大嫌いなボクでも、パチンコをたまにやってしまうような変な魔力があるので本当に怖いです。
パチンコはギャンブルじゃないとか言う人もいますが、まぁギャンブルでしょ。
幸いボクは、麻雀も競輪、競艇もまったく興味が沸かないし魅力に感じないので良かったですが、依存してしまう素質はあると思うのでこれからも関わらないようにしていきます。
話が逸れましたが、弟の問題点として、今でも親の金でパチンコに行くことがあるようです。
頻度はそんなに多くない、と言っていますがそういう問題なのかなぁ?と思います。
もっとやることあるんじゃないかな、と感じます。
ちなみにギャンブル自体を否定する意図はありません。
趣味として予算の範囲でやるのは別にいいと思いますよ、本当に。
ゴルフは良くてパチンコは駄目、とか別にないし、人類の歴史を見ても最終的にはゲームをやるのが人間の性だと思います。
ボクもゲームはやりますしね。
何事も程度問題なので、適度に予算の範囲で遊んでいきましょう。
まとめ
今回は『独身・無職・実家暮らしの課題を考える』というテーマで書いてきました。
- 実家暮らし・無職の弟の存在は、家庭内に静かな緊張感と孤独をもたらしている
- 兄として感じるのは、諦め、苛立ち、そして“どうにもできない現実”への無力感
- 就職氷河期世代や「8050問題」は、家族単位では解決できない社会課題でもある
- 親の甘やかしや支援の継続が、時に本人の自立を遠ざける要因になることも
- 「働くこと」「社会と関わること」が当たり前ではない人たちが、確かに存在している
- 家族は簡単に見捨てられない。でも、関わり方を見直すことは必要だと感じる
- 自己責任論で片づけるのではなく、個々の背景に目を向ける視点が求められている
- 誰もが「当事者」になる可能性があるという現実を、他人事として流してはいけない
この記事は、弟への文句を書くためのものではありません。
ですが、ちょっと愚痴っぽくなってしまった感はありますね。
読んでいただいた方はありがとうございます。
ボクもどうしようもない気持ちを言語化したかったので、書いてよかったです。
この日本社会において、「独身・無職・実家暮らし」の大人が増えているという現実と、そこにある葛藤や限界について、他人事ではなく当事者として少しでも正直に綴ってみたかったのです。
もしかすると、同じような立場で悩んでいる人が、この記事を読んで「うちだけじゃないんだ」と思ってくれたら嬉しいです。
この記事が、誰かの「気づき」や「行動のきっかけ」になれば、さらに幸いです。
家族であっても誰かを変えることは難しいです。
でも、自分がどう関わるかは、自分で決めることができます。
だから僕は、これからもできる範囲で、弟との関係と向き合っていこうと思います。
そして、少しでも前向きな方向に進むよう、模索を続けたいと思います。
あなたの家族は、どうですか?
何か感じることがあれば、コメントやXなどでシェアしてくれたら嬉しいです。
今回はここまで。
読んでいただきありがとうございました。
より良い人生にしていきましょう\(^o^)/
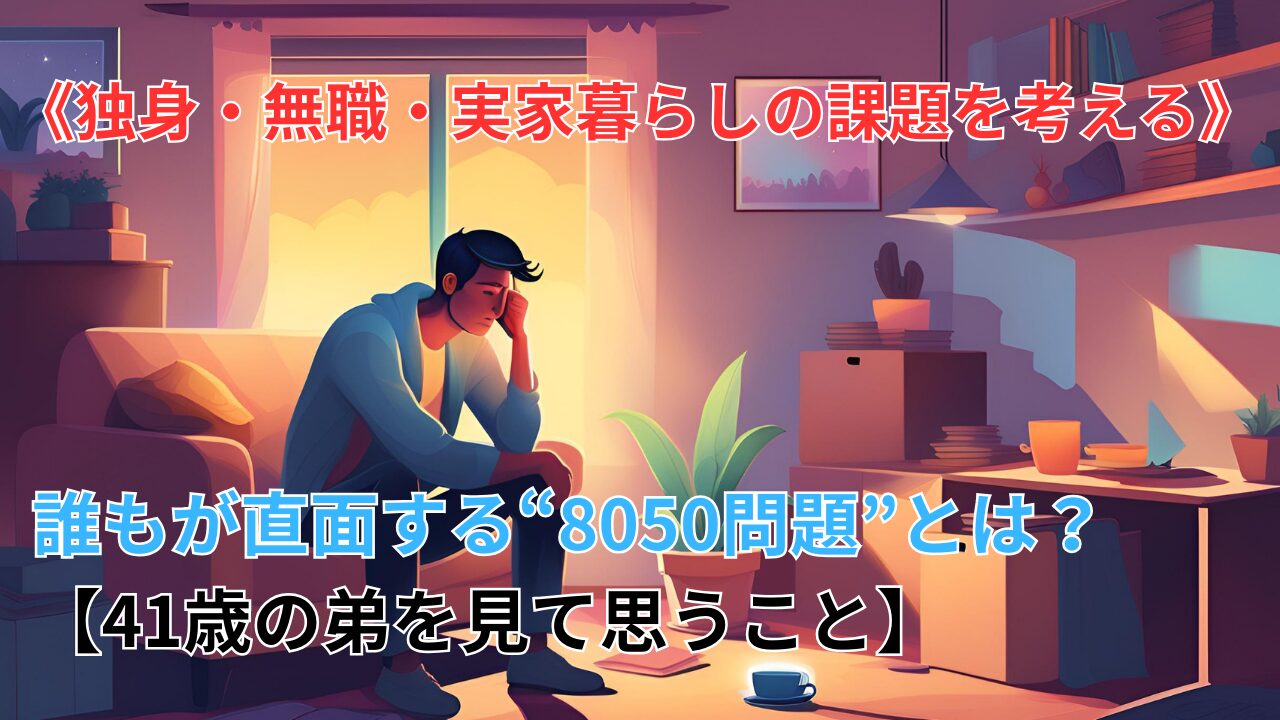



コメント