おはようございます!ミヤビです(^^)
2025年も気づけば後半戦ですね。
月日の流れるのは早いものです。
テクノロジーの進化がますます加速する中で、ボクたちの生活も大きく変わろうとしています。
ボクはまだ実行できていないですが「マイナ免許証」が導入されていたり、「生成AIの実用化フェーズ」など、身近な変化がいよいよ現実となり始めています。
今日は「2025年最近のテクノロジー動向」について、個人的に気になったポイントを具体例と共に解説していきます!
マイナ免許証が導入されていた

今回の記事を書こうと思ったきっかけがこれなんですよね。
2025年3月24日から、「マイナンバーカードと運転免許証の一体化(通称:マイナ免許証)」が導入されていたことはご存知ですか??
マイナンバーカードと運転免許証を1枚にまとめることで、本人確認や行政手続きがスムーズになるという大きなメリットがあります。
マイナ免許証の仕組みとは?
マイナ免許証は、物理的なカードこそ1枚ですが、ICチップの中に「マイナンバー」と「運転免許証情報」の2つが紐付けられています。
これにより、警察の免許確認や、役所での手続きが一枚のカードで完結するようになります。
- マイナンバー情報 → 公的手続き
- 免許証情報 → 運転資格証明
- ICチップ → セキュアな情報管理
生活者にとってのメリット
ボクたちの世代(40代)以上の年代は、こうしたデジタル行政に対して「便利そうだけど不安もある」という気持ちが強いですが、実際に使ってみると意外にシンプルだったりするものです。
まずは「健康保険証の一体化」から試してみるのもアリですね。
マイナ保険証にも切り替え済みですが何にも不便ないですね。
生成AIがビジネス現場に“当たり前”に
続いて押さえておきたいのが「生成AIの本格実用化」です。
2023年〜2024年にかけてブームとなったChatGPTや画像生成AIですが、2025年8月時点では「ビジネス現場での活用」が当たり前になりつつあります。
生成AIの利用シーン
具体的なシーンを挙げると、
- 企画書や提案資料の下書き作成
- 顧客対応のチャットボット自動生成
- デザインのアイデア出し
などが挙げられます。
ボクの会社のある部署でも生成AIを活用し、商品の受注対応などに活用した事例があります。
【生成AI活用フロー】
- プロンプト入力(指示文を書く)
- AIが初稿を作成
- 人が修正・ブラッシュアップ
ボク自身もブログ記事のアイデア出しや構成を考える時にChatGPTを活用していますが、“ゼロから考える負荷”が劇的に軽くなります。
気をつけたいポイント
ただし、AIは“万能”ではありません。
特に「情報の正確性チェック」や「独自性を加える部分」は人間の仕事です。
AIを“アシスタント”として使いこなすスキルが、これからのビジネスパーソンに必須になってきますね。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の波は地方にも

これまで首都圏中心だったデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が、いよいよ地方自治体や地方企業にも押し寄せています。
ボクの仲間で地方の行政と仕事している人からも聞いた話です。
- 紙ベースの業務をタブレットに移行
- オンライン商談システムを導入
- クラウド会計ソフトを使った経理効率化
- Canva Proのセミナーを自治体の中で実施
といった動きが活発化しています。
「地方がDX化が遅い」とも言われますが、場所によってはどんどん進めているところもありそうです。
地方DXが加速する背景
特に2025年は「スマートシティ構想」の流れもあり、地方都市でも5G・IoTを使った実証実験が行われています。
【地方DXの推進要素】
- 人手不足 → DX化による業務効率
- 地方自治体 → 国の支援策を活用
- 中小企業 → オンライン化で販路拡大
地方在住の方でも「ウチには関係ない」では済まされない時代が来ています。
まとめ
今日は「2025年最近のテクノロジー動向」について書いてみました。
- 2025年3月から「マイナ免許証」が本格導入済み
- マイナンバーカードと免許証が1枚に統合され利便性アップ
- 生成AIは企画・対応・デザインなどビジネス現場で活用が当たり前に
- AIは“万能”ではなく、正確性や独自性のチェックは人の役割
- 地方自治体や企業でもDX化が加速している
- 人手不足や支援制度が地方DXを後押し
- テクノロジーの波は都市だけでなく全国に広がっている
こんな感じですかね。
- マイナ免許証で行政手続きがシンプルに
- 生成AIが仕事の“相棒”として当たり前に
- 地方にもDX化の波が本格到来
これらに共通するのは「便利になるのは歓迎。でも最終的には“使いこなす人間側の意識”が大事」ということです。
便利なものを便利に使いこなしてこそ、テクノロジーは私たちの人生を豊かにしてくれます。
今回はここまで。 読んでいただきありがとうございました。
より良い人生にしていきましょう\(^o^)/
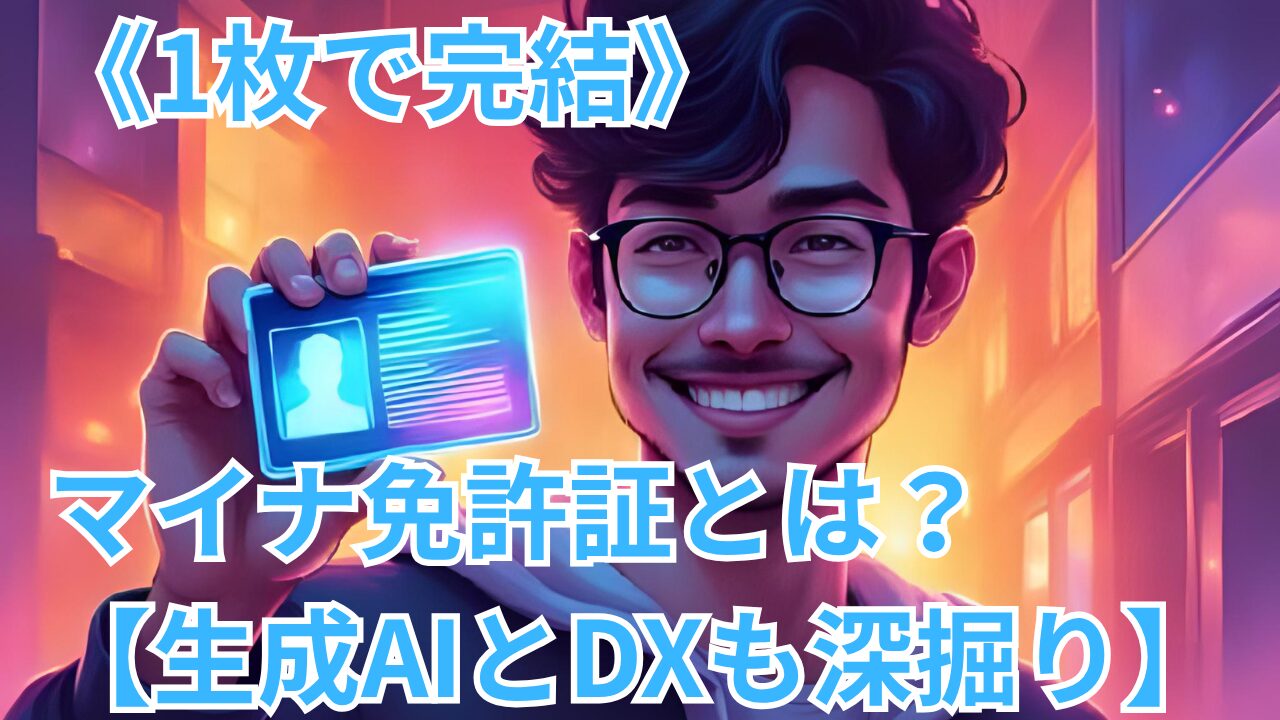


コメント