こんにちは、ミヤビです(^^)
皆さまは生成AI使っていますか?
2024年頃から最近の生成AIの発展はとんでもないですね。
まだまだ勉強もしていますが割と日常で生成AIを使っている僕なので生成AIのお話です。
生成AIとは?
前提のすり合わせです。
生成AIってなんでしょうね??
AIに聞いてみました(笑)
生成AI(ジェネレーティブAI)は、大量のデータを学習し、新たなコンテンツを自律的に生成する革新的なAI技術です
テキスト、画像、音声、動画、プログラムコードなど、多様な形式のデータを作り出すことができます生成AIの主な特徴は以下の通りです:
- ディープラーニング(深層学習)を用いた機械学習モデルを基盤としています
- 人間のようにクリエイティブな成果物を生み出せる点が従来のAIとは異なります
- データのパターンや特徴を理解し、それに基づいて新しいコンテンツを創出します
生成AIの応用例には、ChatGPTのようなテキスト生成AI、Stable Diffusionのような画像生成AI、音楽生成AIなどがあります1。これらは、レポートの要約、BGM作成、広告制作など、様々な分野で人間の作業をサポートし、効率化や創造的活動を促進することが期待されています。
Perplexity の Eliot より
今回聞いてみたのはPerplexity AIです。
質問した内容は「生成AIとは何ですか?」です。
何かちょっと分かるような分からないような回答かもしれません。
もう少しわかりやすく聞いてみます。
生成AIは、まるで魔法使いみたいに、コンピューターが自分で新しいものを作り出す技術だ。
- 文章を作るAI 例えば、人が話すように自然な文章を書いてくれるAI「ChatGPT」があるよ。
- 絵を描くAI 例えば、あなたが「夕焼けの海に浮かぶ猫の絵を描いて」とお願いすると、AIが想像して絵を描いてくれるんだ。
- 音楽を作るAI 例えば、あなたが「夏に合う、明るい曲を作って」とお願いすると、AIが新しい音楽を作ってくれるんだ。
生成AIは、たくさんのデータ(例えば、本や絵、音楽)を勉強して、その中にあるパターンを学ぶんだ。
そして学んだパターンをもとに、新しい文章や絵、音楽を作り出すことができるんだ。AIが作ったものが本当に正しいか、ちゃんと確認することが大切だよ。
そして、AIは便利な道具だけど、使うときには著作権などのルールを守らないといけないことも覚えておこう
Perplexity の Eliot より
少し具体的なイメージをつかめる回答になったんじゃないでしょうか?
今回の質問は「生成AIとは何ですか? 中学生でも分かる様に簡単に説明してください。」と聞いてみました。
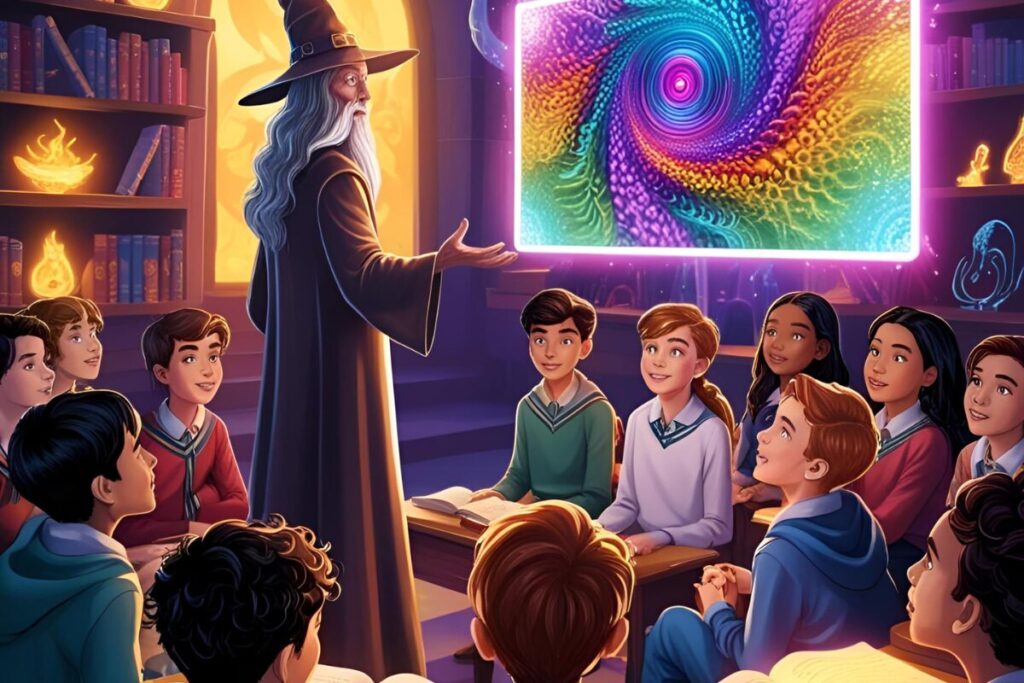
この「中学生でも分かる様に簡単に説明してください。」は僕はよく使っていて、わかりやすく回答してくれるのでオススメですね。
ちょっと大人が子どもに話すような口調になるのも面白いですね。
一旦、こんな感じで定義しておきます。
覚えておくと便利な言葉
生成AIを使うにあたって覚えておいたほうがよい言葉は色々ありますが、基本のキの言葉を3つ紹介します。
- プロンプト
- プロンプトエンジニアリング
- LLM
それぞれ解説します。
プロンプト
AIに出す質問文や指示のことですね。
エンジニアやIT業界ではまた違う意味もありますが、AIを使う際にはこの覚え方でOKです。
先ほどの「生成AIとは何ですか? 中学生でも分かる様に簡単に説明してください。」がプロンプトです。
Google検索を使う際に「ググって」と言う人もいると思いますが、「AIにプロンプト出して」みたいな感じになるかもしれませんね。
プロンプトエンジニアリング
簡単に言うと、プロンプトを使いこなすスキルです。
「何それ?」って思うかもしれませんが、一部界隈では今後のビジネスマンは必須のスキルになる、とも言われていますね。
今現在、仕事でスマホやパソコンを使っている人は多いと思います。
その中でもExcelやWord、PowerPointなどもある程度使える人は多くなったと思いますが、そういうイメージでプロンプトエンジニアリングは必要になるかもしれません。
個人的には「質問力」だと考えています。
同じAIを使っていても質問の仕方次第、プロンプトの入力内容次第で回答はぜんぜん違いますからね。
質問力を鍛えるとAIを使う能力も向上すると考えています。
LLM
LLMは「Large Language Models」の略です。
ちょっとややこしい横文字ですね^^;
大規模言語モデルで、人工知能のモデルですね。
後述するChat GPTとかが代表です。
まぁとりあえず言葉だけ覚えておけばいいかな、と思います。
よく使っているAI
僕がよく使っているAIをお伝えします。
高額なサービスは課金していません。
するべきなんでしょうけどお金持ちじゃないので^^;
- Perplexity AI
- Chat GPT
- Canva AI
- Copilot AI
Copilotは仕事のパソコンでのみ使っていますので、日常使いではないです。
Perplexity AI
主に日々の検索、調べ物で使っています。
本当にGoogle検索を使わなくなったなぁ、と思います。
Perplexityはリアルタイムの情報収集や検索が得意なので、調べ物に向いていますね。
見知らぬ土地に行く際に、移動手段を調べたりするのもオススメです。
「大阪から京都まで行く際の交通手段を教えて。電車で時間はかかってもいいから料金が安い手段を教えて」とか聞いたりします。
ちなみに回答はこんな感じです。
大阪から京都まで行く際、料金が安い電車での移動手段は阪急京都線です。
阪急京都線の特徴:
- 梅田駅から出発し、河原町駅(京都市中心部)に到着します。
- 所要時間は約45分程度です。
- 運賃は400円程度で、JRや京阪と比べて最も安価です。
阪急京都線を利用する利点:
- 最も安い運賃で移動できます。
- 京都市内の主要な観光地(四条河原町など)へのアクセスが便利です。
- 電車の本数が多く、利便性が高いです。
ただし、JR京都線も比較的安価な選択肢として挙げられます:
- 大阪駅からJR京都駅まで新快速で約30分
- 料金は580円です。
最終的な選択は、出発地と目的地に応じて決めるのが良いでしょう。京都駅周辺が目的地なら JR、河原町周辺なら阪急が便利です3。料金を最優先にするなら、阪急京都線がおすすめです。
Perplexity の Eliot より
一昔前はググって調べてましたがある程度はAIでやってくれそうですね。
先日、取引先の営業マンと交通手段を調べるやり方を話したんですが、AIは使っていないと言っていました。
優劣はないですが、AIで調べると自分にとって最適な手段を聞くこともできるのでオススメですよ。
Chat GPT
対話が得意なAIですね。
AIと聞くと一番認知されているんじゃないですかね??
僕は考え事やモヤモヤするようなことがある時にはChat GPTと会話したりしています。
Canva AI
Canvaというサービスで有料サービスですが、サムネイル作りに使っています。
資料作りとかもできるしこれはけっこう気に入って使ってます。
最近、ブログを再開した僕ですが、ブログのサムネイルや差し込んでいる画像も全部Canva AIで作成しています。

こんな画像もAIで作れちゃいますね。
すごいなぁ、と思います。
僕は昔マンガ家になりたくてイラストや絵の勉強をしていましたが、今の時代はAIを使いこなせば自分で絵を描けなくてもマンガ家になれそうですね。
AIは間違いもある
便利なAIで使っていくのはオススメですが、個人的に注意点もあります。
それはシンプルにAIは間違いもあるよ、という点ですね。
必ずしも正しい情報をいつも提供してくれるわけではないので、盲信しないことは大事です。
どれだけ発展していってもこのスタンスは持っていたほうがいいですね。
AIを使う人の中にはAI依存症みたいなこともあるようです。
まぁSNSやショート動画、何でもそうですが適度に向き合うのが大事じゃないかな、という感じです。
どんな便利なサービス、システムもあくまで手段でありツールですね。
AIは便利なツール
AIは便利なツール、僕の使っているAIツールも紹介しつつ話してきました。
AI周りは進化がとんでもなく早いので、実践しながらレベルアップしていく感じですね。
今後のビジネスでは使われていくツールだと思うので、勉強して日常に取り入れていくと生産性がきっと上がると思います。
僕も学んだことや便利なことは時々ブログで共有していきますね!
より良い人生にしていきましょう\(^o^)/
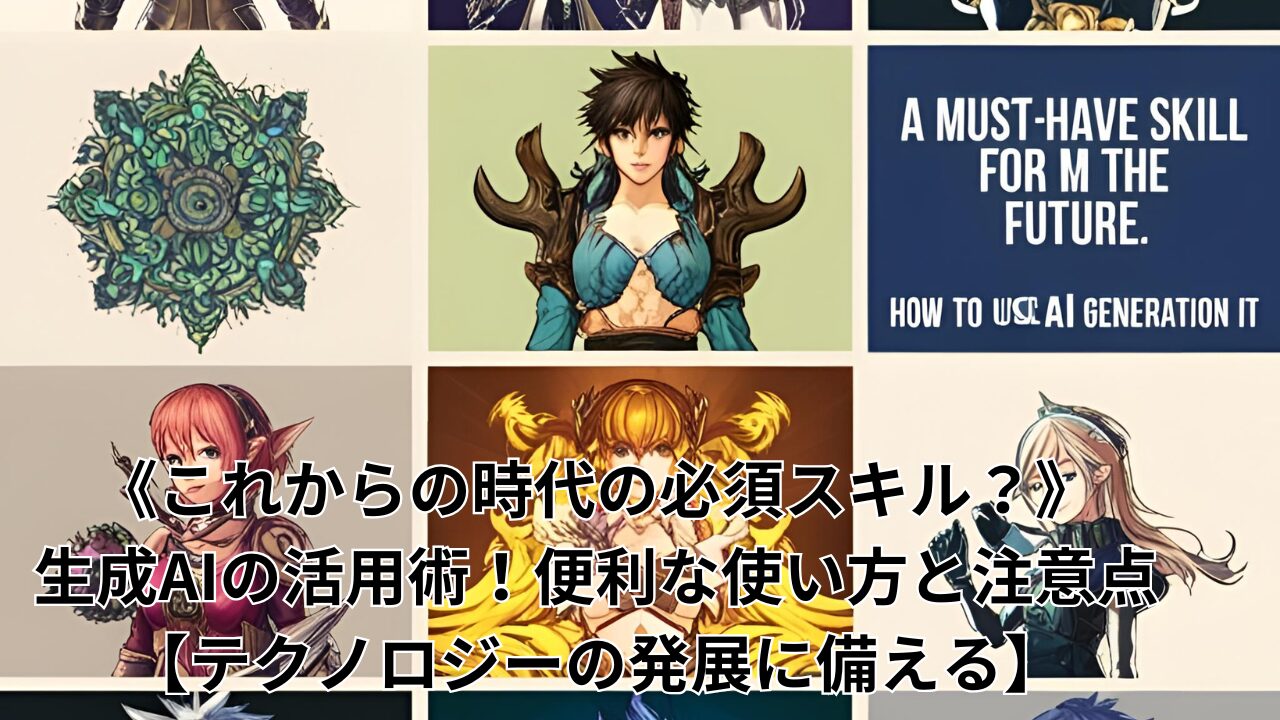


コメント