おはようございます!ミヤビです(^^)
今日は「サードプレイスと仲間を持つ大切さ」というテーマで書いていきます。
ボクは仲間に恵まれているなぁ、ありがたいなぁ、と本心から毎日感じるので、感謝の意味も込めて言語化しておこうと思います。
仲間が同じ資格に合格した件
この話を書こうと思ったきっかけは一つじゃないんですが、直近では会社の仲間が資格試験に合格したことがきっかけです。
ボクはITパスポートという資格を2024年11月に受験して、合格しました。
自分のITスキル向上、仕事で活かせるかな、と考えて受験しましたが、それになぜか会社の仲間が影響されたみたいでした。
何か理由はよくわからないけど(笑)
ボクがきっかけになって受験をしたそうなので、良い影響があったようなので良かったなぁ、と思っています。
合格までしたので本当にすごいなぁ、尊敬するなぁ、と思いました。
元上司も影響を受けて勉強しているようでして、仲間っていいよな、と思う今日この頃です。
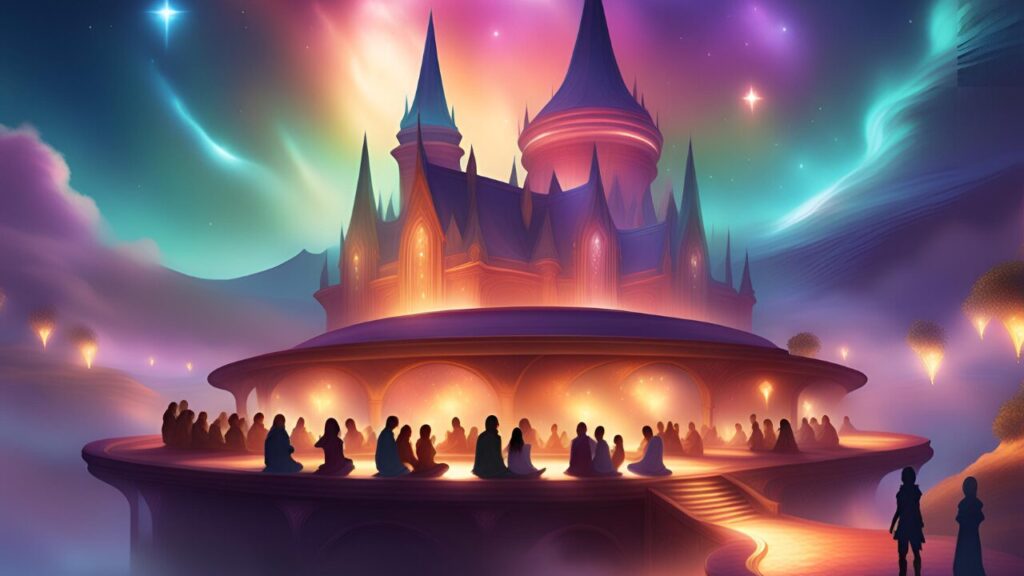
そんなつもりはありませんでしたが、自分がきっかけになって多少は影響を与えた、というのも何だか嬉しくて喜びを感じました。
余談ですが、資格試験の勉強は賛否両論あります。
資格なんかとってもムダ派、はいますし、それも理解できます。
ただ、勉強をするプロセスはムダではないと考えています。
それ自体が何かをやり切るチカラの証明になりますし、勉強する習慣が身につけば人生の他のことにもきっと活かせるので、挑戦してみるのはオススメですね。
仕事と家庭以外のサードプレイスはあるか?
さて、ITパスポートに関しては会社の仲間の話でした。
会社の仲間、人間関係が恵まれているということは本当に大事です。
いつの時代も仕事の悩みの大多数は人間関係だと思うので、良質な人間関係が形成されているかどうか?は極めて重要ですね。
企業という組織も、個の集まりであり、個人個人が文化を作り風土を醸成していきます。
良い悪いではなく、自分に合う合わないもあるので、人間関係が良くないなぁ、と思う組織にいるなら離れたほうがいいです。
見極めるためにも、多様な価値観の人と関わることが重要です。
あなたは、会社と家族以外に過ごす場所、いわゆるサードプレイスはお持ちですか?
サードプレイスとは、自宅(ファーストプレイス)や職場・学校(セカンドプレイス)とは異なる「第三の居場所」を指し、ストレスから解放されリラックスできる空間を意味する。
アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグが1989年の著書『The Great Good Place』で提唱した概念で、現代社会における人間関係の希薄化やストレス増加への対処策として注目されている。主な特徴
- 中立性と平等性
経済的・社会的地位に関係なく誰でも参加可能で、自由な交流が可能。- アクセスのしやすさ
自宅や職場の移動経路上にあり、気軽に立ち寄れる立地。- コミュニケーション重視
堅苦しい議論ではなく、気軽な会話や遊び心のある交流が中心。- 常連と新規参加者の共存
頻繁に訪れる常連が雰囲気を形成しつつ、新規参加者も受け入れる。- 居心地の良さ
家庭的な雰囲気で、派手さよりくつろぎを重視した空間。具体例
- カフェ(スターバックスはサードプレイス提供をコンセプトに採用)
- 居酒屋やコミュニティスペース
- シェアオフィス(WeWorkなど)
- 地域のサークルや趣味のコミュニティ
注目される背景
自動車依存型社会の進展で自宅と職場の往復が主流となった米国で、人間的な交流の場の必要性が指摘された。
日本でも働き方の多様化やストレス社会の進行により、自分らしく過ごせる場への関心が高まっている。Perplexity の Eliot より
ボクが思うサードプレイスは、単なる空間ではなく、一緒になにか志を共有できる仲間がいること、です。
そういう意味では物理的な場所ではなくても良くて、オンラインコミュニティとかもありです。
サードプレイスという概念は、最近になって注目されていることだと思いますし、ボクも意識してサードプレイスを作ろう、とか思ったことはないです。
人生が充実しているなぁ、と考えた時に、よくよく考えるとサードプレイスが複数あるな、と気づきました。
過去から現在まで、ボクのサードプレイスの例を紹介していきます。
行きつけのワインバー
今は断酒中なのでめっきりお酒を飲まなくなりました。
過去には行きつけのワインバーがあって、月に1~2回くらいでしたが一人でも飲みに行ったりしていました。
店主と仲が良くなって、居心地が良い空間でした。
類は友を呼ぶ、じゃないんですが、そういう場所にいると、自然とお客さん同士でも仲良くなったりします。
ボクもそこで7名くらいの仲間ができて、ご飯食べに行ったり飲みに行ったり、カラオケ行ったりするくらいになりました。
今でもたまに連絡取っていて、また飲みに行きましょう、と話したりします。
仕事外の人たちで、普段は交わらない業種や年齢の人もいて、学びや気づきが深いです。
かけがえのない大切な人たちばかりで、ボクのことも大事にしてくれていると感じます。
オンラインコミュニティ
以前に、テックキャンプというオンラインスクールでプログラミングスクールを学んだことがあります。
スクール卒業後も、気の合う仲間と交流が現在も続いていて、オフ会にも参加したことあります。
こちらも志が高い人が多くて、多種多様な人がいらっしゃいます。
仕事も年齢も色々で、やはり普段、会社と家族としか交流していないと触れ合わない人たちと交流できるのはすごく楽しく、面白いです。
前向きで人生をより良くしていこう、という人たちばかりなので、自分も気が引き締まります。

会社と家庭しかない人のリスク
余計なお世話だよ!と言われそうですが、サードプレイスがない人のリスクについても少し考えておきます。
要するに、仕事と家庭しかない人のリスクです。
仕事と家庭に集中することが悪い、と言いたいわけではありません。
個人的に最大のリスクは「視野が狭くなる」ということだと思います。
価値観が偏る、考え方が広くならない、とも言えます。
同じ会社にいて、特に長く同じ会社にいるとそれなりに居心地がいいはずです。
それは悪いことじゃないんですが、いつの間にか認知が歪んでいきやすいです。
多様な価値観に触れづらくなり、おかしなことにも気づきづらいリスクもあります。
日々忙しくてるいそうなりがちなのも理解できますが、同じ人とばかり過ごすのはボクはリスクだな、と考えています。
まとめ
今日は「サードプレイスと仲間を持つ大切さ」というテーマで書いてきました。
- 仲間の存在は、自分に良い影響を与え、時には自分が誰かのきっかけになることもある
- 資格試験のような挑戦は、一人で頑張るものではなく、互いに刺激し合える仲間の存在が力になる
- 人間関係の良し悪しは、職場環境の満足度を大きく左右する重要な要素
- サードプレイスは「物理的な場所」ではなく、「心が安らぎ、ありのままの自分でいられる空間」
- オンライン・オフライン問わず、多様な人と交流することで、新しい価値観や学びが得られる
- サードプレイスには、ゆるやかなつながりの中に「安心感」と「前向きな刺激」が共存している
- 仲間とは、肩書きや職種を超えたつながりを持てる存在であり、自分を成長させてくれる鏡のようなもの
- 志を共有できる仲間と出会うことで、人生はもっと豊かに、充実したものになる
こんな感じですかね。
仕事や家庭だけじゃない、もうひとつの「安心できる居場所」。
そして、そこで出会う「人生を前に進めてくれる仲間」。
このふたつがあるだけで、人生の幸福度ってグンと上がるんじゃないかなと思っています。
だからこそ、意識的にサードプレイスを探したり、仲間との関係を大事にしたりするのって、すごく意味があることだと思います。
あなたにとってのサードプレイス、そして大切な仲間はどこにいますか?
ちょっとだけ立ち止まって考えてみるのも、悪くないかもしれません(^^)
ボクでよければ皆さんとお互いにサードプレイスになれたらいいな、と思っています。
今回はここまで。
読んでいただきありがとうございました。
より良い人生にしていきましょう\(^o^)/



コメント