おはようございます!ミヤビです(^^)
今日は「継続の大切さと難しさ」について考えていきたいと思います。
結論から言えば、継続は人生を豊かにする最強の習慣だけれど、同時に人間が一番苦手とするものでもあります。
ボク自身もここ最近、ブログを書く頻度が減ったことや、自分が続けてきた習慣がボロボロと崩れてきていました。
ブログを書き続ける中で、「続けること」の価値と苦労を日々実感していますし、最終的にはやっぱり継続しかない、と痛感しています。
今回は、数字や世の中のデータも交えながら、継続の本質を掘り下げていきます。
継続が人生を変える理由

継続は「信頼」と「成果」を生む最大の武器です。
信頼が積み重なる
人は「言ったことをやり続ける人」を信用します。
過去にも触れたことがありますが、一貫性のある行動は信頼を生み、人間関係や仕事の基盤になります。
成果が積み重なる
1日1ページの読書でも1年で365ページ。
週3日の筋トレでも1年で150回近くの積み重ねになります。
小さな継続の積み重ねが、大きな変化をもたらすのです。
継続が難しい理由
しかし、多くの人が「三日坊主」で終わってしまいます。
ボクのこのブログも数年前に作ってから何度も書いたり書かなくなったりの繰り返しです。
脳の仕組みが変化を嫌う
人間の脳は現状維持を好みます。
新しい習慣は「エネルギー消費」と捉えられ、拒否反応を起こします。
モチベーションの波
季節や環境の影響でやる気は必ず波打ちます。
モチベーション頼みでは続けられないのです。
ボクも毎日日記をつけていますが、特に秋の今頃は気分が乗らなかったり体調を崩したりしがちです。
継続を可能にする工夫
ここからは、ボクが実際に意識している工夫を紹介します。
小さな習慣から始める
「1日10分だけ読書」「腕立て5回」など、負担が少ないスタートが大切です。
まずは習慣化することが大事なので、小さく始めて段々と負荷を上げていくのがオススメです。
見える化で達成感を得る
カレンダーに✔をつける、アプリで記録するなど「続けた証拠」を残すこと。
下の図解のように、視覚化は継続のモチベーションを支えます。
習慣の見える化サイクル
- 小さな行動を設定する
- 記録を残す(✔やアプリ)
- 達成感を味わう
- 次の日もやる気が出る
仲間と共有する
SNSやコミュニティに「今日もできた」と報告すると、習慣が強化されます。
お互いの活動報告を聞いたり、励まし合うことは意外と有効ですよね。
継続の閾値(しきいち)と方向性

この記事を書こうと思ったのは直近聞いたあるVoicyがきっかけです。
尊敬する大河内先生です。
無料で聴けるのでもし興味ある方は聴いてみてほしいです。
努力の方向性
この中で使われていた継続の方向性と閾値という言葉が印象的でした。
まず努力の方向性が間違っていないか?の確認。
変な例えですが、プロの野球選手を目指すのに、サッカーの練習をする人はいません。
しかし、ビジネスや勉強ではこういうことが容易く起きてしまいます。
自分のやっていることの方向性が正しいのか?
定期的に見直す必要があるな、と感じます。
努力の閾値
閾値(しきいち)って言葉は個人的には最近よく聞くようになった気がします。
ボクはいつもこの閾値に到達する前にやめてしまっているんだろうなぁ、と感じます。
ブログを4ヶ月連続投稿しましたが、特にブログなんて1年続けたとて結果が出るわけもないです。
仕事をしながらブログを書くとか、それだけで確かに大変ですが、コツコツと続けていこうと思います。
まとめ
今日は「継続の大切さと難しさ」について書いてきました。
- 継続は「信頼」と「成果」を積み重ねる最大の武器
- しかし脳の仕組みやモチベーションの波で続けるのは難しい
- 小さな習慣から始めて「見える化」することで続けやすくなる
- 仲間やコミュニティと共有すると習慣が強化される
- 努力は「方向性」を間違えないことが大切
- 「閾値(しきいち)」に到達する前にやめず、続けることが結果につながる
こんな感じですかね。
継続は「力」そのものです。ただし、難しさもセットで存在します。
だからこそ、小さな習慣化・見える化・仲間との共有といった工夫が必要になります。
本当に偉そうにボクがいえることではありません。
ボク自身に対する戒めでもあるし、毎日DAY1の気持ちでやっていこうという意味合いも込めて書いていきました。
今回はここまで。
読んでいただきありがとうございました。
より良い人生にしていきましょう\(^o^)/


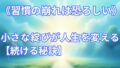

コメント