おはようございます!ミヤビです(^^)
4月の半ばですが寒かったり暖かかったりですね。
体調不良には気をつけて、無理せず毎日頑張っていきましょう!
今日は人事の仕事に関わるボクが、自分のアウトプットの意味を込めて、採用活動の今のアレコレを考えて書いてみます。
採用市場の今
今日の記事を書こうと思ったききっかけは3つあります。
- 退職代行が使われているニュースを見た
- 自分の仕事で採用活動を難しく感じる
- 副業でクライアントワークの案件探しをしてみた結果
自分の仕事にも関係ある領域なので、それぞれを考えてみます。
コロナ禍を経て、世の中の働き方は劇的に変化しました。
その変化は採用活動にも確実に影響を与えています。
2025年現在、企業と個人の関係性はより流動的・柔軟になり、従来の「終身雇用」や「会社に忠誠を尽くす働き方」は、過去のものになりつつあると言われていますね。
新卒採用の変化、退職代行の台頭、副業の普及、という3つの観点から、現在の採用活動の実情と課題を掘り下げてみたいと思います。

新卒採用の「通年化」と「個人主導」の時代
かつて日本企業の新卒採用は、「一括採用・一斉入社」が常識でした。
一度入社した会社に骨を埋める、なんていうのが普通でしたね。
しかし今、その仕組みは確実に揺らぎ始めています。
一因としては、大学生のキャリア観の多様化があります。
起業や長期インターン、海外留学などを経験する学生が増え、卒業時点で「すぐに就職」するという前提が薄れてきています。
また、企業側も優秀な学生を確保するために、通年採用やジョブ型採用を導入する動きが増えています。
たとえば外資系企業や一部のメガベンチャーでは、ポジションごとに求めるスキルを明確に提示し、時期を問わずに採用するというスタイルが定着しつつあります。
これにより、「とりあえず4月入社」といった曖昧な採用が減り、より合理的かつ個人に合わせた採用が進んでいます。
新卒採用の“個人化”が進む中で、企業には以下のような視点が求められます。
- 自社が学生にとってどのような魅力を提供できるか
- スキルや価値観をどう見極めるか
- 入社後のキャリアパス設計が明確になっているか
従来のように「ポテンシャル採用」で広く人材を集める時代から、より精度と柔軟性を重視した採用へとシフトしているんですね。
ボクの周りでも転職する人も普通にいますし、新卒で採用されて終身雇用、なんて時代はとっくに終わっているのかもしれません。
就職氷河期世代のボクは、自分の経歴もあり新卒で採用されたことはありません。
その結果、望むと望まないにかかわらず、自然と転職してきたし色々な会社で働いてきました。
今の会社の勤務は長いですし、満足感高く働けているのは本当にありがたいです。
その上で、「このままでいい」とは思っていないので、もっと頑張っていこうと毎日思います。

退職代行の台頭
最近、メディアなどでも話題となっている「退職代行サービス」。
皆さんは御存知でしょうか??
退職代行ってけっこう良くできたビジネスモデルのようです。
利用者は20〜30代を中心に拡大しているみたいですね。
「もう自分で退職を言い出すのは時代遅れ」とさえ言う人もいるとかいないとか。
個人的には、退職の挨拶くらいは自分から言い出したほうがいいんじゃないかなぁ、とは思います。
需要があるからできているサービスなので、それを利用すること自体にあれこれ言うつもりはありません。
退職代行は一見、採用活動とは無関係に思えますが、企業にとっては“離職者からのフィードバック”の一形態とも言えます。
本来、円満退職できる職場であれば、第三者を介さずとも退職意思を伝えることは難しくないはずです。
退職代行を使うということは、それだけ「言い出しにくい」「職場にストレスがある」「引き止めやパワハラを恐れている」人がいるという現実の裏返しでもあります。
つまり、退職代行の利用者が多い職場は、「採用してもすぐ辞める」「組織文化に課題がある」といった負のスパイラルに陥っている可能性があるかもしれませんね。
採用活動の質を高めるためには、「入社の瞬間」だけでなく、「退職の瞬間」まで視野に入れた一貫した人材マネジメントが求められます。
ボクも非正規雇用の採用活動に携わっているので、退社の瞬間も踏まえた採用活動が必要だな、と思います。
副業の一般化
一昔前までは、「副業=本業に集中していない」とネガティブな印象を持たれがちでした。
しかし今、副業はキャリア形成やスキルアップの一環として、多くのビジネスパーソンにとって当たり前の選択肢となっています。
政府が「働き方改革」の一環として副業・兼業を後押ししたこともあり、企業側も就業規則を見直す動きが加速。
今や副業OKの企業も増えました。
ボクの働いている会社も、以前は副業禁止でしたが、現在は副業OKになっています。
スタートアップやIT企業では、「副業している人材のほうが視野が広く、自己管理能力も高い」という評価もあるようです。
開業届を出しているかどうか?という違いもあるかもですが、個人事業主として働く側面があるので、サラリーマンマインドではなく、経営者マインドが身につくんじゃないかなぁ、と思います。
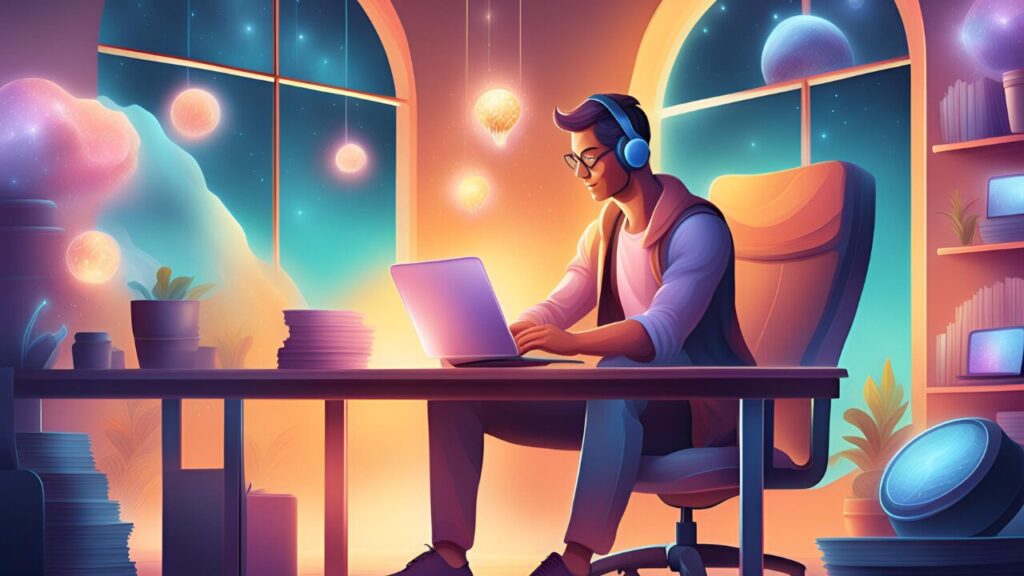
一方で、企業側には懸念やリスクもありますね。
たとえば、情報漏洩のリスク、労働時間の管理が難しい、**本業とのコンフリクト(利益相反)**など、慎重な姿勢を崩さない企業も少なくないようです。
某大手自動車メーカーで働いている知人が言っていましたが副業禁止という会社もまだまだあります。
採用活動においては、応募者の副業経験をどう評価するか、また副業を希望する人材をどう受け入れるか、企業側の姿勢が問われる時代になったと言えるかもしれません。
余談ですが、ボク自身副業に興味があって色々やってきました。
最近はクライアントワークを探してみましたが、2ヶ月くらい探して結局見つからず、それはそれで難しいなぁとも感じています。
副業探しや今やっていることはまた別の機会に触れてみようと思います。
まとめ
今日は仕事や自分の副業探しから思う、採用市場の今について考えてみました。
- 新卒採用は「通年化」「個人主導」の流れが加速し、企業も柔軟な採用スタイルへの対応が求められている
- 退職代行の普及は、職場のコミュニケーションや組織文化に課題があることのサインかもしれない
- 採用活動は「入社」だけでなく「退職」までを見据えた視点が必要
- 副業は今やスタンダードな選択肢であり、キャリア形成の一環としてポジティブに評価されつつある
- 企業には、副業に対する柔軟性とリスク管理の両立が求められる時代に
- 応募者の副業経験や志向性をどう評価するかは、今後の採用活動の重要なテーマ
- 採用活動に携わる自分自身も、変化に適応し続けながら、自分なりの成長と挑戦を重ねていきたい
こんな感じですかね。
副業、新卒の通年採用、退職代行――いずれも共通しているのは、「働く側の主体性が増している」という点です。
もはや採用は「企業が選ぶ側」ではありません。
候補者から選ばれる存在であるためには、企業側も透明性の高い情報発信、柔軟な制度設計、そして心理的安全性のある職場づくりが欠かせません。
これからの採用活動のキーワードは「関係性」。
一度採用したら終わりではなく、入社前から信頼関係を築き、入社後も継続的にエンゲージメントを高めていく視点が、より重要になっていくでしょう。
企業が人を選ぶ時代から、人が企業を“選び続ける”時代へ。
採用の意味が、根本から問われている今だからこそ、あらためて「人をどう迎え、どう送り出すか」を見つめ直すべき時期なのかもしれませんね。
ボクは人と人との関係性にこそ幸せがあると思っているので、泥臭く人間関係にこだわりながら毎日生きていきます。
今回はここまで。
読んでいただききありがとうございました。
より良い人生にしていきましょう\(^o^)/



コメント